.jpg?auto=format&fit=max&w=3840&q=50)
青森の方言の特徴は?「~びょん」や「どさ・ゆさ」などかわいい言葉を紹介!
この記事では、青森県の方言の特徴や代表的な言葉をご紹介!「どさ・ゆさ」や「め・け」など短い単語や文が特徴の青森の方言。「~びょん」や「めんこい」などかわいい方言も紹介するので、フレーズを覚えて、青森旅行の際に使ってみてはいかがでしょうか?

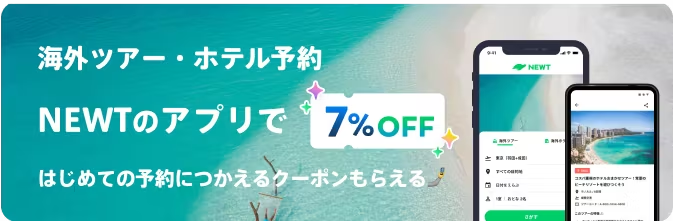
この記事では、青森県の方言の特徴や代表的な言葉をご紹介!「どさ・ゆさ」や「め・け」など短い単語や文が特徴の青森の方言。「~びょん」や「めんこい」などかわいい方言も紹介するので、フレーズを覚えて、青森旅行の際に使ってみてはいかがでしょうか?
\NEWTでおトクに旅行しませんか✈️/
青森の方言の特徴は?

青森県の方言といえば、なまりが特徴的で、聞き取るのが大変難しいことで全国的に有名な方言ですよね。そして、一般的に多くの方が思い浮かべる青森の方言といえば「津軽弁」でしょう。
しかし、青森県の方言は津軽弁だけではありません。青森では大きく分けて3つの方言が話されており、津軽地方で話される「津軽弁」、南部地方で話される「南部弁」、下北半島で話されている「下北弁」があります。同じ青森県内の方どうしであっても、方言が違うと全く通じない言葉もあるそうですよ!
津軽弁をはじめ、青森の方言全体に言える特徴は、「会話中の単語と一文が極めて短いこと」。単語や文が短くなった理由に、冬に厳しい寒さとなる気候が挙げられます。極寒かつ吹雪となる日もある環境で、口数をなるべく少なくしたいという人々の工夫から、短くなったと言われています。これは青森の方言に限らず、秋田県など冬の自然環境が厳しい東北の方言全体に見られる特徴です。
なお、青森県の中心部に位置する青森市や弘前市などの地域では、津軽弁と標準語を混ぜたような言葉も多くなっています。
青森の方言は地域によって異なる!
青森県では、大きく分けて「津軽弁」「南部弁」「下北弁」の3つの方言が話されています。それぞれどのような特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。
津軽弁
津軽弁は、青森の西側の津軽地方で話されている方言です。「青森の方言」と聞いて真っ先に全国の人が思い浮かべるのは津軽弁でしょう。
津軽弁は、標準語と比べて一文が極めて短いのが大きな特徴で、独特の響きとリズムがあります。その独特の響きや単語・語尾は標準語とかけ離れており、「まるで外国語のように聞こえる」という人もいるほどです。
また、濁音が多用され、力強い口調にも聞こえますが、その力強さの中にも親しみやすさや温かみを感じる方言です。
南部弁
南部弁は、青森の東側の南部地方で話されている方言です。南部弁は津軽弁と比べると、柔らかいおっとりとした話し方が特徴です。
また、動詞の語尾に「べ」「べえ」「きゃ」「ちゃ」が用いられることも特徴。南部弁は、岩手県や中部地方でも共通する表現が見られるため、県外の人でも親しみやすい方言といえるでしょう。
下北弁
下北弁は、青森の北側の下北半島で話されている方言です。下北弁は津軽弁よりなまりが優しく、わかりやすい方言だと言われています。
北海道の方言や津軽弁と似ている一方、独自の表現や音韻も見られます。
\NEWTでおトクに旅行しませんか✈️/
旅行先で使いたい!青森のよく使われる方言

ここからはぜひ知っておきたい代表的な青森の方言をご紹介。これらの方言を知っておけば、青森旅行の際、地元の方々との交流が深まること間違いなし!
どさ・ゆさ
「どさ」は「どこに行くの?」の意味、「ゆさ」は「温泉に行くところです」の意味です。
「どさ」は「どごさ行ぐの」の省略形で、「ど」が「どこ」、「さ」が方向を指しています。また、「ゆさ」は「湯さ行ぐどご」の省略形で、「湯」が「温泉(銭湯)」、「さ」は方向、「行ぐどこ」は「行くところ」を指しています。
長い文章を短く表現するという東北方言の特徴がはっきり出ている、有名な津軽弁です。
<会話例>
「どさ?」=どこに行くの?
「ゆさ」=温泉(銭湯)に行くところだよ。
わ・な(おめ)
「わ」は「私」「僕」といった一人称、「な」「おめ」は「あなた」の意味です。こちらも長い文章を短く表現する、という津軽弁の特徴が出ています。
ちなみに、初対面の人にいきなり「な」や「おめ」と言うのは「おまえ」に近い意味になり、失礼になってしまいますので、気を付けてくださいね。
<会話例>
「これで、わどなは、けやぐだね!」=これで、私とあなたは、友達だね!
なして
「なして」は、「どうして」という疑問を表す言葉です。青森だけでなく、北海道や東北地方、新潟、中国地方の一部など、さまざまな県で使われている方言です。
この表現は会話の中で理由や原因をたずねる際や、疑問がある際に使われます。「どうして」よりもフランクな表現で、フレンドリーな印象を与えます。
<会話例>
「なして急に黙っちゃったの?」=どうして急に黙っちゃったの?
まいね
「まいね」は、「ダメ」という否定の意味を表す言葉です。否定の意味ですが、柔らかなニュアンスから青森の言葉の温かさを感じられる言葉ですね。
<会話例>
「仕事をサボっちゃまいねね」=仕事をサボってはダメだよ
「あの店、ちょっとまいねかも」=あの店、ちょっとダメかもね
〜さる
自らの意思に関係なく、知らぬ間になんらかの動作が起こってしまった時に使う津軽弁で、北東北や北海道でもひんぱんに使われる方言です。
イメージしやすい例でいうと、携帯電話の発信ボタンを押したつもりはないのに、なんらかのタイミングで知らないうちに発信ボタンが押されてしまい、友達に電話をかけてしまっていた場合、「携帯のボタンが押ささった」と言います。これは、「電話をかけるつもりはなかったけれど、知らないうちに電話のボタンを押してしまっていた」という意味です。
「自分のせいではなく、無意識に起こってしまった」というニュアンスになり、周りも「それはしょうがないね」と納得するため、大変便利な方言です。
<会話例>
「あの人の踊り、見らさるね」=あの人の踊りは、見るつもりはなくても見てしまうね
「紙に書かさった!」=(ペンの蓋が開いていたなどで)知らないうちに紙に書いてしまっていた!
あずましい
「あずましい」は「心地いい」「居心地がいい」といった意味をあらわす言葉です。青森だけでなく、東北地方の一部、北海道でも使われる方言です。「あずましくない」と否定形をともない、「落ち着かない」といった意味で使う場合もあります。
<会話例>
「このゆ、あずましいなぁ」=この温泉は気持ちいいなあ
めやぐ
「めやぐ」は直訳すると「迷惑」という意味になりますが、日常の会話では「ごめんなさい」や「すみません」といったニュアンスで用いられます。
また、「こんなに良くしてもらって、迷惑をかけて申し訳ない」という謙虚な気持ちから、「ありがとう」という意味で思いやりと最大限の感謝を表す際にもよく使われます。
<会話例>
「めやぐだばって、牛乳、どこさある?」=すみません、牛乳はどこですか?
「こした良いもんもらって、めやぐだじゃ」=こんな良いものをくれてありがとう
め・け
「め」は「おいしい」、「け」は「食べて」の意味です。「け」は「食べて」のほかにも、イントネーションに違いをつけて「かゆい」「ちょうだい」「心配」などさまざまな意味があります。
この「め」「け」のように、津軽弁にはまさに長い文章を短く表現するという特徴を顕著に反映した、一文字の表現が多くあります。
<会話例>
「めじゃー!」=おいしい!
「もっとけ!」=もっと食べなさい
たげ・たんげ
「たげ」「たんげ」は「たくさん」「とても」「すごく」の意味で、強調するときによく使われます。同様の意味を表す言葉として「ずっぱど」「わや」「のたんこ」などさまざまな言葉があります。
<会話例>
「たんげ、めぇ!」=すごくおいしい!
「たんげ忙しかったじゃ」=とても忙しかったよ
しばれる
「しばれる」は「とても寒い」という意味で、漢字で書くと「凍れる」となり、まさに凍てつく寒さを表現した言葉です。北海道や秋田など一部の東北地方でも使われる方言です。特に冷え込んだ朝や寒波が来た日など、冬の会話に使いやすい言葉ですよ。
<会話例>
「今朝はずいぶんしばれるね」=今朝はすごく寒いね
青森のかわいい・おもしろい方言

ここでは青森ならではのかわいい響きや面白い響きの方言をご紹介。日常の会話で気軽に取り入れられる言葉もあるので、ぜひ青森県民と会話する際に使ってみてくださいね!
〜びょん
「びょん」は語尾につける言葉で、「だろう」「かもしれない」という推量の意味を表します。また、「だよね」といったニュアンスでも用いられますが、どこか音感としてもかわいさがある方言です。
「びょん」を使った津軽弁の難解な例文として有名なのが「せばだばまいねびょん」。「せばだば」は「それじゃあ」「そしたら」、「まいね」は「ダメ」、「びょん」は「だよね」という意味を指し、文章全体としては「それじゃあダメだよね」という意味になります。
<会話例>
「今日は仕事遅く終わるびょん」=今日は仕事が遅く終わるかもしれない
〜っこ
青森の方言は名詞の後に「~っこ」をつけて、愛称や親しみを込める表現があります。生き物やかわいらしいものにだけ使うのではなく、無機質なもの・ことや場所など、さまざまなものに「~っこ」をつけます。
「~っこ」が付くだけで、柔らかいかわいらしい言葉に聞こえますよね!
<使用例>
「犬っこ」=犬
「お茶っこ」=お茶
「角っこ」=(物や場所の)角
かちゃくちゃね
「かちゃくちゃ」は「散らかっている」という意味です。「かちゃくちゃない」「かちゃくちゃねぇ」もよく使われる表現で、「頭の中がごちゃごちゃする・散らかっている」という意味から転じて「イライラする」というニュアンスでも使われます。
<会話例>
(散らかっている部屋を見て)「なんぼかちゃくちゃね」=すごく散らかっているね
めんこい
「めんこい」とは、青森の方言で「かわいい」「かわいらしい」という意味で、北海道や東北地方で広く使われています。人・動物や物への愛らしさや親しみを表現でき、会話に温かい印象を与えます。
<会話例>
「そのかばん、めんこいね」=そのかばん、かわいいね
「めんこい赤ちゃんだねぇ」=かわいい赤ちゃんだね
しゃっこい
「しゃっこい」は「冷たい」という意味で、北海道や東北地方で広く使われています。水や氷が思ったよりも冷たい時や、寒さで手が冷たくなった時などによく使います。
<会話例>
「この水、しゃっこくて、めぇなー」=この水、冷たくておいしいな
「手がしゃっこい」=手が冷たい
わんつか・あんか
「わんつか」「あんか」は「少し」「ちょっと」という意味です。
津軽弁で「少し」という意味を表現する場合、量によって言い方が変わります。少しだけの場合は「わんつか」「あんか」、ほんの少しだけの場合は「あんつか」、本当に少しだけの場合は「さんじゃらっと」を使います。
<会話例>
「もうわんつか味が濃くてもいい」=もう少し味が濃くてもいい
「わんつか待ってけ!」=もうちょっと待ってちょうだい!
へば
「へば」はイントネーションによって意味が異なる言葉です。語尾でイントネーションが上がる場合、「またね」「バイバイ」という意味になります。
一方、語尾でイントネーションが下がる場合、「それだったら~?」「そしたら~?」と疑問を意味する際に使います。たとえば、「へば、どうすればいいんず?」であれば、「それだったら、どうすればいいの?」という意味になります。
なお「へば」は、基本的に親しい間柄の人にしか使わないため、ビジネスシーンなどでは使わない言葉となっています。
<会話例>
「へばねー!」=またねー!
ちょす
「ちょす」は津軽弁で「触る」「いじる」という意味で、北海道や東北地方で広く使われています。
<会話例>
「そったにスマホちょせばまね」=そんなにスマホをいじるんじゃない
青森の方言を旅行先で使ってみよう!
この記事では、津軽弁を中心に青森の方言をご紹介しました。青森の方言は標準語と大きく異なり、理解するのが難しいイメージがありますが、少しでも言葉を知っておくと、親しみがわくでしょう。
ぜひ気軽に取り入れて、青森旅行で現地の方との交流を楽しみ、旅の思い出を増やしてくださいね!
cover photo by PIXTA


