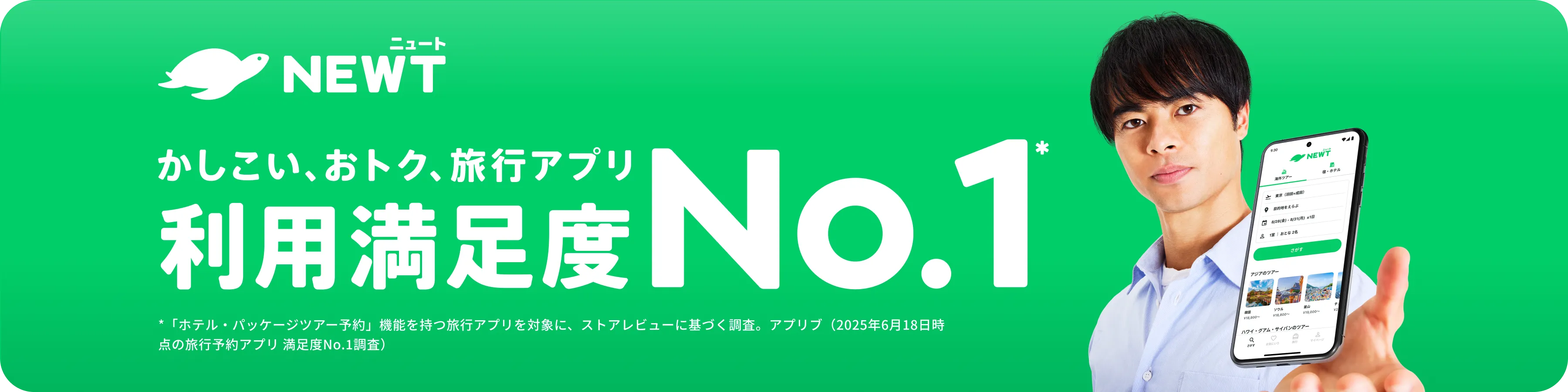日本でラッコに会える水族館はどこ?唯一の場所の鳥羽水族館とみどころも解説
この記事では、日本でラッコに会える水族館を紹介します。日本中の水族館にたくさんいた人気者のラッコ。しかし今では会えるのは1カ所だけになってしまいました。その理由と、ラッコのかわいい習性も解説します!


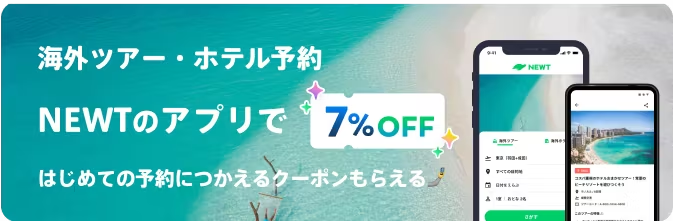
この記事では、日本でラッコに会える水族館を紹介します。日本中の水族館にたくさんいた人気者のラッコ。しかし今では会えるのは1カ所だけになってしまいました。その理由と、ラッコのかわいい習性も解説します!
もっとみる
- 過去にラッコがいた水族館一覧
- 輸入禁止で激減
- 水族館での繁殖は難しい
- 北海道には野生のラッコが
- 日本の水族館のラッコは残りわずか2頭
- ラッコを飼育しているのは鳥羽水族館だけ
- 珍しい生き物が多い鳥羽水族館
- 鳥羽水族館のラッコ
- メイのプロフィール
- キラのプロフィール
- メイとキラの見分け方
- ラッコの展示エリアは極地の海ゾーン
- ラッコの観覧方法が変更に
- 伊勢志摩の観光のついでにもおすすめ
- ラッコ撮影のコツ
- 速めのシャッタースピードがポイント
- 動体追従や連写を活用
- レンズをガラスに近づける
- かわいいラッコのここに注目!
- ラッコはどんな生活をしている?
- お気に入りの石をポケットに入れている
- ラッコの毛は哺乳類で一番多い
- 水に潜るのは大変
- 毛づくろいをしないと寒い
- 体に油がつくのを嫌がる
- バンザイや目隠しをする理由
- たくさんの餌を食べる
- 寝るときは海藻にくるまる
- 手を繋いで寝ることも
- 鳥羽水族館にラッコを見にいこう!
\NEWTでおトクに旅行しませんか✈️/
ラッコはどんな動物?

ラッコはイタチ科の哺乳類。英語ではSea Otter(海のカワウソ)と呼ばれます。『ラッコ』というのはこの生き物を表すアイヌ語。本来はアイヌ語でも海のカワウソを表す『アトゥイエサマン』と呼んでいますが、夜にこの言葉を使うとカワウソが化けて出るため夜はラッコと呼ぶようになったと伝わっています。
ラッコはイタチ科ではもっとも大きい種類ですが、海洋哺乳動物では最小。オットセイやマナティー、イルカなどほかの海洋哺乳類にはない特徴も持っています。
そんなラッコの亜種は3つ。住む海域や体の作りに違いがあります。
チシマラッコ(アジアラッコ)
千島列島やコマンドルスキー諸島、北海道根室沖や襟裳岬でも見られるラッコ。亜種のなかでは体がもっとも大きく、頭が広く、鼻骨が小さいのが特徴です。
カリフォルニアラッコ
カリフォルニア中央部の太平洋沿岸に住むラッコです。住む海域が狭く、個体数も3,000頭ほどと最も少ない種類。体は小さめで頭部が狭く、歯が小さいのが特徴です。
アラスカラッコ
アメリカのアラスカ州などに住むラッコ。保護のためワシントン州やカナダのブリティッシュコロンビア州沿岸へも移されています。水温4℃から10℃の冷たい海で生活し、海岸から10km以内の岩礁やジャイアントケルプ(コンブ)の森がある場所を好むのが特徴です。
見た目はチシマラッコとカリフォルニアラッコの中間で、下顎骨が長いのが特徴。日本の水族館で見られるのはこのアラスカラッコです。
\NEWTでおトクに旅行しませんか✈️/
日本の水族館からラッコが減ったのはなぜ?

ある程度の年齢の方なら、ラッコは日本中の水族館にたくさんいるというイメージを持っているのではないでしょうか。しかし今ではわずか1カ所を除いて、どの水族館に行ってもラッコに会うことはできなくなってしまいました。
一時は最多28の施設に122頭もいたラッコ
日本の水族館にラッコが登場したのは1982年。最初は静岡県の伊豆・三津シーパラダイスでした。かわいいラッコはすぐ大人気に。日本中の水族館で展示されるようになります。最盛期は1994年。この当時は全国28の施設で122頭のラッコが飼育されていました。
過去にラッコがいた水族館一覧
こちらが過去にラッコがいた水族館です。実際に訪れてラッコに会ったという方も多いのではないでしょうか。
- オホーツク水族館(北海道網走市)
- おたる水族館(北海道小樽市)
- サンピアザ水族館(北海道札幌市)
- ひろお水族館(北海道広尾町)
- 登別マリンパークニクス(北海道登別市)
- 青森県営浅虫水族館(青森県青森市)
- 鶴岡市立加茂水族館(山形県鶴岡市)
- マリンピア松島水族館(宮城県松島町)
- アクアマリンふくしま(福島県いわき市)
- アクアワールド茨城県大洗水族館(茨城県大洗町)
- 鴨川シーワールド(千葉県鴨川市)
- サンシャイン水族館(東京都豊島区)
- よみうりランド(本社所在地:東京都稲城市)
- 八景島シーパラダイス(神奈川県横浜市)
- 江の島水族館(神奈川県藤沢市)
- 下田海中水族館(静岡県下田市)
- 伊豆・三津シーパラダイス(静岡県沼津市)
- 新潟市水族館 マリンピア日本海(新潟県新潟市)
- のとじま水族館(石川県七尾市)
- 金沢ヘルスセンター(金沢サニーランド)の水族館(石川県金沢市)
- 南知多ビーチランド(愛知県美浜町)
- のんほいパーク 豊橋総合動植物公園(愛知県豊橋市)
- アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)
- 太地町立くじらの博物館(和歌山県太地町)
- 海遊館(大阪府大阪市)
- 須磨海浜水族園(兵庫県神戸市)
- 宮島水族館(現:みやじマリン)(広島県廿日市市)
- 屋島水族館(香川県高松市)
- マリンワールド海の中道(福岡県福岡市)
- 長崎水族館(長崎県長崎市)
- 長崎バイオパーク(長崎県西海市)
- 大分マリーンパレス水族館『うみたまご』(大分県大分市)
- いおワールドかごしま水族館(鹿児島県鹿児島市)
輸入禁止で激減

日本の水族館でラッコが激減している主な原因は輸入禁止措置です。
そもそもラッコはとても数が少ない生き物。18世紀以降に毛皮を取るために過度に狩猟され、残り約2,000頭まで激減したという歴史があります。それに追い打ちをかけたのが1989年のアラスカ・プリンス・ウィリアム湾でのエクソンバルディーズ号の原油流出事故。海が油に覆われたため生息地が広範囲で破壊され、せっかく数が増えはじめていたラッコが約3,000頭も命を落としてしまいました。
深刻な絶滅の危機に陥った野生のラッコを守るため、1998年にアメリカは国内法でラッコの捕獲や輸出を原則禁止とします。続いて2000年には国際自然保護連合(IUCN)がラッコを絶滅危惧種に指定。その結果、ワシントン条約でラッコの輸出が禁止され、水族館が新しくラッコを輸入することはできなくなりました。
水族館での繁殖は難しい
自然の環境では、ラッコは広い範囲で活動しています。とくに繁殖期にはオスがメスを求めて移動。この行動がラッコの繁殖には大きな意味を持っています。しかし水族館ではラッコの自然な活動を再現できず、繁殖させることがとても難しいのです。またラッコはストレスに弱く、繁殖のために水族館を移動させることも簡単ではありません。
海外からの輸入が途絶え、国内での繁殖も難しいため、水族館のラッコは徐々に減少。数が減ると遺伝的な問題もあって繁殖がさらに難しくなるという悪循環で、日本の水族館からラッコはほとんどいなくなってしまったのです。
北海道には野生のラッコが
北海道東部の霧多布岬には2016年ごろから野生のラッコが戻ってきています。北海道で見られるのは、水族館にいるアラスカラッコとは異なるチシマラッコ。2018年からは赤ちゃんの姿も見られるようになり、数は増えているといわれています。
では北海道のラッコを捕獲して水族館で飼育できるのかというと、現状ではそれも不可能です。ワシントン条約では輸出だけでなく、野生のラッコの捕獲も世界的に禁止しています。これはラッコの乱獲を防ぐために必要とされる措置。動物園や水族館で観察することで野生生物を大切にする気持ちも育つといわれていますが、今のところ水族館のラッコを増やす方法はないのです。
日本の水族館のラッコは残りわずか2頭
これまで日本のラッコは3頭でした。しかし2025年1月に福岡県福岡市のマリンワールド海の中道のラッコ(リロ)が死亡してしまい、日本の水族館で見られるラッコは2頭だけとなってしまいました。
ラッコを飼育しているのは鳥羽水族館だけ

残り2頭のラッコがいるのは、三重県鳥羽市の鳥羽水族館です。鳥羽水族館は1955年に開業し、2025年には70周年を迎えるという歴史ある水族館。約1,200種類以上の飼育種類数は日本一です。
水族館としては珍しく順路がないのも特色。入場者は好きなルートで見て、気に入ったところには何度も戻ることができます。
珍しい生き物が多い鳥羽水族館

鳥羽水族館といえば珍しい生き物がいるのも特徴です。ジュゴンを飼っているのは日本で鳥羽水族館だけ。また日本でマナティーを見ることができる水族館は4館ですが、そのうちアフリカマナティーに会えるのも鳥羽水族館だけです。
そしてラッコの飼育も日本唯一。そのため鳥羽水族館は大きな注目を集めています。
鳥羽水族館のラッコ

鳥羽水族館のラッコは2頭。メイとキラという名前で、どちらもメスです。
メイのプロフィール
メイは2004年5月生まれ。鳥羽水族館で生まれました。
性格は好奇心旺盛でやんちゃ。一方で神経質で怖がりな一面もあります。
キラのプロフィール
キラは2008年4月生まれ。南紀白浜アドベンチャーワールドで生まれました。
性格はマイペースでおっとりしています。
メイとキラの見分け方
メイとキラはいくつかの特徴で見分けることができます。
メイの特徴
- 若干大きい
- 大人びている雰囲気
- 全体的に白い
- 鼻に白い傷跡
- ヒゲが短く整っている
キラの特徴
- やや小さい
- 体形がシュッとしている印象
- お腹周りの毛が濃く黒い
- 鼻の毛が黄色っぽい
ラッコの展示エリアは極地の海ゾーン
鳥羽水族館は、海獣の王国、古代の海、伊勢志摩の海・日本の海、ジャングルワールド、人魚の海などたくさんのエリアに分かれています。そのなかでラッコがいるのは、極地の海ゾーンです。ここは極寒の世界に生きる動物たちのライフスタイルを見せる展示ゾーン。ラッコの他にもイロワケイルカやバイカルアザラシなどがいて人気のエリアとなっています。
ラッコの観覧方法が変更に
鳥羽水族館では2025年3月17日からラッコ水槽の観覧方法が変更されました。
これまでラッコ水槽は自由に見学できましたが、日本で唯一ラッコが見られる水族館になったこともあって水槽前がとても混雑するように。変更後は観覧ルートに沿って移動しながら見学することになりました。
極地の海コーナー入口から観覧列に並び、係員の誘導にしたがって待機。水槽前の観覧スペースには約10名ずつ案内されます。水槽前の観覧スペースで1分間、自由な場所から見学し、時間になったら係員の誘導に従って水槽前から移動します。
これまでは水槽の前に長時間張り付いている人がいて満足に見られないことも。新しい観覧方法が発表されるとSNS上には多くの歓迎の声が上がっています。
伊勢志摩の観光のついでにもおすすめ

鳥羽水族館がある鳥羽市は、伊勢神宮がある伊勢市から電車で20分ほど。伊勢神宮や二見浦、志摩のリアス海岸といった有名な観光スポットのついでに立ち寄ることができます。みどころがいっぱいなので伊勢志摩には2泊3日ほどの観光スケジュールで訪れるのがおすすめですよ。
鳥羽水族館の基本情報 | |
|---|---|
住所 | 三重県鳥羽市鳥羽3-3-6 |
電話 | 0599-25-2555 |
営業時間 | 9:30〜18:00 (最終入場は17:00まで) GW(4/29~5/5)、夏季(8/1~8/31)の期間は9:00~17:30(最終入館は16:30) |
休業日 | 年中無休 |
アクセス | JR近鉄鳥羽駅から徒歩で約10分 伊勢ICから車で約30分 |
料金 | 大人 2,800円 小中学生 1,600円 幼児(3歳以上) 800円 |
公式サイト | |
ラッコ撮影のコツ

鳥羽水族館でラッコを見られるチャンスは1回につき1分間。写真撮影のためにじっくり粘っている時間はないので、コツを知っておいて確実にかわいく撮りましょう!
速めのシャッタースピードがポイント
ラッコはゆったり浮かんでいるイメージがありますが、実は意外と素早く動く動物。遅いシャッタースピードでは動きがブレてしまいがちです。水族館は意外と暗く、シャッタースピードが遅くなりやすいので注意してください。
ラッコを撮るときはISO(感度)を上げるのがコツ。そして調整できるカメラなら速めのシャッタースピードにします。できれば1/500秒以上の速度にしてください。これで被写体ブレを防ぐことができます。
動体追従や連写を活用
ラッコは予測不能な動きをしがち。一般的なオートフォーカスモードではピントが外れてしまうことがよくあります。機能を選べるカメラなら動体追従モードを使うようにしてください。また連写してベストショットを後から選ぶのもおすすめ。動きを追いきれないようならなるべく高画素で広めに撮影しておいて、後から周囲をトリミングする方法もあります。
レンズをガラスに近づける
鳥羽水族館のラッコは水槽のガラス越しの撮影になります。この場合、ガラスに映り込む光の反射で全体がボヤッとしがち。映り込みを防ぐためには、レンズをガラスにグッと近づけるのが有効です。
かわいいラッコのここに注目!

せっかくラッコを見にいくなら、いろいろな行動の理由なども知っておいた方が楽しめます。ここではかわいいラッコのユニークな秘密を紹介しましょう!
ラッコはどんな生活をしている?
ラッコの1日はどのような配分なのでしょうか。水に浮いているイメージがあるラッコは実際に餌を獲るために潜る時間以外はほとんど水上で浮かんだまま過ごします。平均的な1日の時間配分はこんな感じです。
- 潜って餌を獲る:8時間
- 浮いたまま毛づくろい:5時間
- 浮いたまま休息:11時間
餌を獲るのに8時間、毛づくろいに5時間もかけるのですね。その理由もこの後じっくり解説します。
お気に入りの石をポケットに入れている
ラッコは道具を使うというとても珍しい習性を持った動物。貝やウニを食べるときには、お腹の上に置いた石に打ちつけて割ります。霊長類以外の哺乳類で道具を使うのはラッコだけ。しかもラッコはこの石を毎回拾ってくるのではなく、お気に入りの石をポケットに入れて持ち運びます。ポケットになっているのはわき腹の皮膚のたるみ。水族館でもここに物をしまう芸を披露することがありますよ。
ラッコの毛は哺乳類で一番多い
ラッコは地球の動物でもっとも毛深いといわれています。その密度は1㎠あたり10万本から14万本。全身ではなんと約8億本にもなります。 これは人間の約8,000倍、イエネコの約800倍です。
オットセイやトドなど、もっと古くから海に適応した海洋哺乳類は分厚い脂肪の層で寒さから体を守っています。しかしラッコは海で生きるようになって100万年から300万年ほどしかたっていないため、まだ脂肪層で体温を維持するようには進化していません。そのためふわふわの毛で寒さを遮断しているのです。
水に潜るのは大変
ラッコのふわふわの毛はダウンジャケットのように中に空気を溜め込んで断熱します。しかし空気を含んでいるため体が浮きやすくなるのは難点。餌を獲るために潜るときにはこの毛が邪魔になってアザラシの2倍の体力を使うそうです。
しかも脂肪層なら深く潜っても常に温かいのに対して、ラッコの体毛は深く潜ると空気が押し出されて寒くなってしまいます。そのためあまり深く潜ることはできません。
毛づくろいをしないと寒い
ラッコの毛は中に水が入ると保温効果がなくなってしまいます。そのためラッコは狩りと食事と休息時間以外にはずっと毛づくろいをして毛の中に空気を入れ続けるのです。
毛づくろいは前足のツメを使って行います。まずはていねいに汚れを掃除。同時に口や鼻から毛の間に空気を送り込みます。空気を吹きつけられない顔の毛づくろいは前足でもみ込むように念入りに。背中の方の毛づくろいでは、たるんだ背中の皮膚をお腹まで引っ張ってきて息を吹きかけます。
体に油がつくのを嫌がる
食事中などにラッコがグルグルと回ったり、体をブルっとふるわせることがあります。これは餌からでた水分や油が体につかないようにするため。とくに油がつくと空気の層ができなくなるため、一生懸命に油を飛ばし、前足の爪でかき取ります。
バンザイや目隠しをする理由
_(25169790524)_crop.jpg)
ラッコは水に浮かんでいるとき、手を上げています。これは短い手でバンザイしているように見えますが、実は体を冷やさないための行動です。なぜかというとラッコは手に毛が生えていないから。水に手を浸けてしまうと体温が奪われてしまうので、上げておくしかないのです。
また眠るときには手で目を押さえて目隠しのポーズをすることも。これも手が冷えないための工夫です。
たくさんの餌を食べる
毛による保温効果は他の海洋生物のような皮下脂肪より効率が悪いため、ラッコは体温維持のためにたくさんのエネルギーを消費します。必要なカロリーは1日4,300~5,750kcal。成人男性2人分のエネルギーです。そのため餌の量も多く、1日に体重の20%から30%も食べます。体重40kgのラッコなら1日に約10kg!これは二枚貝だと400個というとんでもない数です。野生のラッコは1日に8時間もかけて猟をし、貝やカニ、ウニなどを食べ続けています。
寝るときは海藻にくるまる
ラッコが好むジャイアントケルプはとても長いコンブ。ラッコは休息している間に海流で流されないようにこのコンブやワカメなどの海藻にくるまり、体を固定して眠ります。
手を繋いで寝ることも

くるまる海藻がない場合、ラッコは仲間とはぐれないように手を繋いで眠ることがあります。鳥羽水族館のメイとキラも近づくと手を繋ぐことがあるそうですよ。
鳥羽水族館にラッコを見にいこう!
以前は日本中の水族館にいたラッコも残りはわずか2頭。メスのラッコの寿命は15年から20年といわれているので、残された時間はあと少ししかないかもしれません。水族館で見られなくなるのは残念ですが、ラッコを守るためには我慢しなければならないことです。野生のラッコが再び増え、水族館でも見られるようになることを期待しましょう。
それまではまさに今がラストチャンス。悔いが残らないよう、ぜひラッコに会いに鳥羽水族館へ行ってみてください。
cover photo by Pixabay
この記事で紹介したホテルはこちら🌟
NEWT(ニュート)ならアプリでかんたんに予約できます🤳 最大5%*ポイント還元!
*会員ステータスに応じてポイントの還元率が異なります。